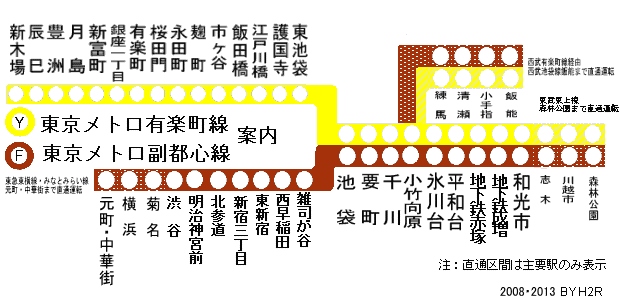| 有楽町線は、昭和42年の運輸省の運輸政策審議会の第11号に基づき、昭和43年、成増−向原(小竹向原)−池袋−飯田橋−永田町−有楽町−明石町(新富町)間の鉄道免許を営団が取得、昭和45年8月19日に着工、昭和49年10月30日、最初の開通区間として、池袋−銀座一丁目間が開通、名前は公募によって決定された。また、有楽町線開通によって丸の内線の混雑緩和に一役買いました。 計画段階のルート選考では、池袋から新橋、溜池、虎ノ門方面へのルートも検討されたが、討論の末、現在の有楽町、銀座方面のルートに決定されました。また、工事段階では、難工事だったそうで、皇居の内堀下や、市ヶ谷付近の外堀下など、軟弱な地盤の場所や、建物を密集している場所の地下を通るところが多く、工事には、一部区間でシールド工法などが採用された。また、当時は、全区間が地下だったため、市ヶ谷に留置線を作って、そこで小検査などを行った。また、桜田門に千代田線との連絡線を建設、主な車両整備は、綾瀬工場で行われていました。開通当初は5両編成で運転されていました。 その後、昭和56年には新富町まで延伸しました。 そして、昭和58年、新富町まで延伸、また、昭和58年6月24日には、郊外側の営団成増まで延伸、後に西武鉄道有楽町線が、小竹向原−新桜台まで開通、営団車による片乗り入れが開始された。当時はまだ、西武鉄道の他線と接続されておらず。西武の車両も準備されたいませんでした。また、営団成増まで開業するのに先だって、5両編成から10両編成に組み替えました。営団成増駅が開業しところから、東武線から営団線にシフトしてくる客が増えてきて、東上線の混雑も緩和してきた時期だった。 昭和62年8月25日、営団成増−和光市間が開通、東武鉄道東上線との相互直通運転が開始、埼玉県西北部から、都心までの利便性がさらによくなり、事実上の複々線状態になり、東武東上線の池袋口の混雑が緩和されました。また、和光市に、検修区ができ、とくに大規模な検査や新車の搬入などが行われない限り、桜田門の渡り線はほとんど使われなくなりました。 そして、昭和63年6月8日、新富町−新木場間が開通、新木場でJR京葉線と接続、舞浜や千葉方面の利便性がよくなり、休日になると。東京デイズニーランドへの家族ずれの客も増えてきました。また、平成9年には新たに臨海副都心線が接続、臨海副都心への利便性が増しました。 平成6年12月、小竹向原−新線池袋間が複々線開業、営団成増開業時に建設した。未使用のトンネルを使用、 |